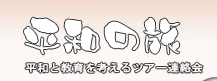�O�D�}��ԗ��Ǝ�f���E�����J�������ق�K�˂�
 �I���������C���𑖂�
�I���������C���𑖂�
�@�y��������f���ɂ������u���̕�W�W���فv�́A2020�N�~�A��̏d�݂œ|��B���̌�p�Ƃ��ē��{�␢�E���̎s������x���ƕ���čČ����ꂽ�̂��u���̕�W�E�����J�������فv�ł��B2024�N9��28���ɃI�[�v�����܂����B�푈�֘A�̔����ق͐�����ǁA���Q�ɓ������œ_�����Ă��~���[�W�A���͋H�ł��B��l�ł͂Ȃ��Ȃ��s���̂������ȏꏊ�Ȃ̂ŁA�c�A�[������ė~�����Ɨ��V�X�e���ɂ��肢���Ă����Ƃ���A���̓x�k�C���@���ҕ��a���c��A�k�C�����a�ψ���̌㉇�ė����������܂����B���͂ǂ����Ă��Ís���Ăق��������̂ŁA�����̃t�F�C�X�u�b�N�Ő�`���A�l�I�ɂ����s��������u���Ƃ��v�����Ɂu�ꏏ�ɂ����܂��v�Ƃ��U�������܂����B����ɉ����ċ��s��O�����v�ȂŁA������O����Ɛe���̂��鎠���M��������v�ȂŁA2���Ԃ̃c�A�[�ɎQ�����邽�߂����œn�����Ă��ꂽ�͖̂{���Ɋ��������Ƃł����B��f���͓��{�S������W�q�ł��閣�͂���t�B���[�h�Ȃ̂ł��B
�@�o�X�́A���{�C���݂�����231�����Ŗk��A���̓��͉H�y�܂Œʏ́u�I���������C���v�𑖂�܂����B68�N���k�C���l�ł���Ȃ��珉�߂đ��铹�Ŋy���������ł��B
8��15���ŏI���Ȃ����������̒n���
�@�u�O�D�}����v�����1945�N8��22���A��������̈����g���D3�ǂ��A���\�A�̐����͍U�����������ł��B�]���Җ�1700�l�̑唼�͏�����q�ǂ��ł����B�ŏ��ɏ��}���ہi���Җ�640�l�A������61���j�����щ��Ō�������܂����B���V���ۂ͗��G���ōU������j�������A���G�`�ɂ��ǂ蒅���܂����B���ҁE�s���s���҂͖�400�l�A�ד��ۂ͏������Ō�������A��q667�l�����𗎂Ƃ����Ƃ���Ă��܂��B���a�̑剡�j��Q��2�̎��ɏ��}���ۂɏ�D�A�t���ʼn��D���Ă������߁A�ߌ��̓�瓦��Ă��܂��B���̕��9�l�̉Ƒ���8��15���ɑד��ۂɏ�D���Ă��܂����B1�T�Ԃ���Ă�����A���͂��̐��ɑ��݂��Ă��Ȃ�������������Ȃ��̂ł��B�ł�����ƂĂ��ЂƂ��ƂƂ͎v���܂���B
�@�R�́u��v�����w���܂����B
�@�P�߂͑��ђ��������n�ɂ��鏬�}���ۏ}��̔�B
�@�����ł͑��ђ�����ψ���̕�����������܂����B
�@�Q�߂͗��G�s�ӂ邳�ƊقŊw�|������A���j�I�w�i�Ȃǂɂ��ă��N�`���\���u�������g�O�D�}��a�̔�v�����w���܂����B3�ڂ͏������S���́u�O�D�}��ԗ�̔�v�Ɏ�����킹����A���̉w���т��הŔԉ��̓W���z�[�������w���܂����B
�@���������ŋ������̂́A1984�i���a59�j�N�Ɏ���܂Ō����J���Ȃ��⍜���W�̂��߂̒��D�̎��n���������Ă��Ȃ��������Ƃł����B������1��Œu���v�Ȃ�25�_�̎��e����������������ŁA�u�ד��ۂ̑D���y�т��̎��ӂɁu�⍜���c���Ă���\���͂Ȃ��v�ƌ��_���A�����ł���ƑS�������A���ɒʒm�����̂ł��B�����ɂ́A�푈����������d�����Ȃ��Ƃ���푈��E�_���_�Ԍ���v���ł����B
�������g�O�D�}��a�̔�i���G�s�j |
�O�D�}��ԗ�̔�i�������j |
�@�Q���҂̒�����u���{���|�c�_���錾��������A�������~���\���Ă���P�T�Ԍ�̂W���Q�Q���ɂȂ��U�����ꂽ�H�v�u���\�A�������������čU�����Ă���͔̂ڋ��łȂ��̂��v�Ƌ^�₪�o����܂���
�@���͎��̂悤�ɍl���Ă��܂��B1945�N2���Ƀ����^�ŘA�����A�����J�A�C�M���X�A�\�A�̂R��]�ɂ���㏈���̉�k���s���܂����B���̍ہA�ĉp�͎����̋]�������Ȃ����邽�߃\�A�̎Q��������v���B�X�^�[�����̓h�C�c�~����3�����ȓ��ɑΓ��Q������邱�Ƃ�A���̌��Ԃ�Ƃ��ē슒���y�ѐ瓇�̋��\�A�ւ̈����n���A�A���Ȃǂ�F�߂����܂����B����͔閧����ł����̂ŁA���ꂪ�\�ɂȂ邱�Ƃ͂Ȃ������̂ł��B��ꎟ���E���ŁA���[�j�����푈�ɏ��������Ƃ��Ă��u�������A�������v�̌������f���������I���Ђ��炷��Α傫�Ȉ�E�ł��B���V�A�����卑��`�A�e����`�̈����������ł��B
�@4��5�����\�A�́A���{�ɑ����\�������̔j����ʍ������B���̒ʍ��ɂ��A���\��������1946�N4��25���Ɏ������邱�ƂƂȂ��Ă��܂����B������H�̒鍑��`���E�ɂ����āA�������̔j���͓G���邩������Ȃ��Ƃ������Ƃł��B���R�\�z���Čx�������Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B������u����I��8��9���ɒ�������j���i�����j���čU�ߍ���ł����v�Ƒ��`����̂́A���\�������e�R�Ɏ��q����F�m���������Ƃ����v�f�Əd�Ȃ�̂ł��B�\�A�̔؍s�͋������������̂ł����A�ꉞ���ۖ@�ɂ̂��Ƃ�A�u���z���v�͂��Ă���̂ł��B�킪����U��Ԃ������Ɂu���ρv�u�����v�Ɩ��̂����̂͐푈�ł���Ȃ���A���z�������Ă���܂���B��P�œ��{�������N�����A���̌�ɐ��z��������͓̂����푈�A���I�푈�A�A�W�A�����m�푈�ɋ��ʂ��Ă��܂��B
�@�\�A���s�������ƂŁA���_�V�x���A�}���ŘA�s���A�����J�������������Ƃ͔���Ȃ��Ă͂Ȃ�܂���B�u�k���v�̓y�Ƃ���鎕���Q���A�F�O���͖k�C���̈ꕔ�ł���A�ǂ������ɕ���ĒD�����s�@��̂ł��B1956�N�̓��\�����錾�œ��\���a��������ꂽ������n���Ɩ��Ă���̂ł�����A�������������ʼn����ɓ��ݏo���̂͐����̐ӔC�ł��B
�@���{�R��{�c�́A8��16���ɂ͐퓬�s�ׂ̒�~��S�R�ɖ��������A�����D�y��ܕ��ʌR�i�ߊ��̔���G��Y�����͊�����88�t�c�ɓ슒�������炷��悤�����Ă��܂��B�\�A�R�͓슒���e�n�ւ̋�P���J�n�A�\�A�R�̓슒���ւ̐i�U�ƂƂ��ɓ��{�R�Ƃ̐퓬���������ƂƂȂ����̂ł��B�k�̒n���ł��B����͐�瓇�Ȃǐ瓇�����l�ł��B���̌��ʁ@�L����P�ł͂P�O�O�l�ȏオ���S�B�^���̓d�b������ȂǏZ���̏W�c�����������܂����B�u�I��v��ł���Ȃ��疯�Ԑl���܂ޑ����̋]���҂��o���̂ł��B
 ���N�l�����J���̗��j�����ށu�a���ƕ��a�̐X�v��
���N�l�����J���̗��j�����ށu�a���ƕ��a�̐X�v���@���O�ɓa���P�F�u�a���ƕ��a�̐X�v��������ǂ�ł���Q�����܂����B���̖{�͎��ɓǂ݂₷���B�����āA�{���ɂ������낢�B�O���͐���������ǂ�ł���悤�Ȋ��o�ł����B�k�C���E��f���i����܂�Ȃ��j�ōs��ꂽ���N�l�����J���̗��j���Ԃ��ɓ`���Ă���܂��B
�@�a���͂��܂��ܗF�l�ƃh���C�u�ŏo�������y��������f���������ŁA��������邱�ƂȂ��a����ꂽ�܂܂ɂȂ��Ă���70�ȏ�̈ʔv�ɑ�������B��������a���̒Njy���n�܂����B
�@���̒n�́A���{�������嗤�ւ̐N����{�i��������1935�N���疼�J���S���̍H�����n�܂�A1941�N�Ɋ�����͐[��Ɩ�������Ԑ[�����Ɖ��̂���A�O������n�q�������k�C���鍑��w���K�т̕���������1938�N���璼�a7�ڂ��̑�̂��A43�N�܂łɉJ���_�������݂��ꂽ�n�������B�a���͑m���Ƃ��āA�H���̉ߒ��ŋ]���ɂȂ��������̒��N�l�̈⍜�@���A�c���ɕԊ҂��鎖�Ƃ��n�߂邪�A����͈�ؓ�ł͂����Ȃ��B �@���ʂƔ��Q�A�N���̉��Q�҂Ɣ�Q�҂͂����ɂ��ĂȂ���A���݂̕ǂ����z���āu�a���v�Ɏ��邱�Ƃ��\�Ȃ̂��낤���B���������A�l����ꏊ����f���Ȃ̂ł��B
�@�ْ��ɏA�C���������������Ă��猻�n�̃t�B���h���[�N�����܂����B
�@�ē��͈ꗬ�̃K�C�h�ł��B
�@���̓I�ɂ悭�킩��܂����B
�@�݂Ȃ�������ЖK�₵�Ă��������B
�i�R�{���r�E�k�C�����j����ҋ��c��j